防衛大を卒業し、しかし自衛隊には任官せず毎日新聞記者になった瀧野隆浩さんの新しい本『自衛隊のリアル』(河出書房新社)を読んだ。豊富な自衛隊人脈をもとに、自衛隊員たちがいったいどのように考え、悩み、そして「戦闘」や「戦死」というリスクに向き合っているのかが、鮮やかに描かれている。
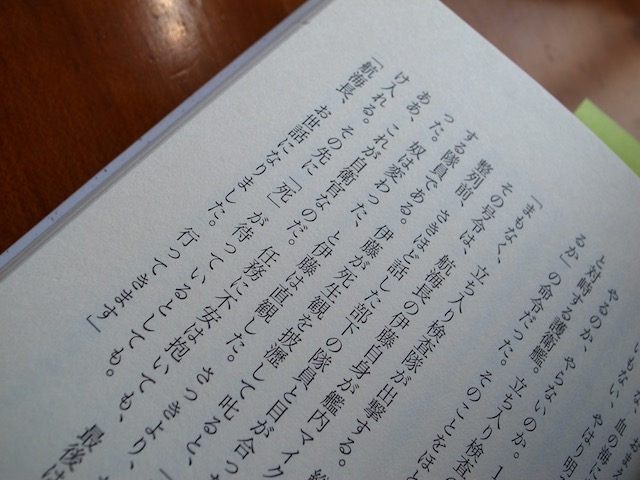
1999年3月、能登半島の沖で不審船が領海侵犯した事件があった。北朝鮮のものと見られるこの船はスピードが速く、海上保安庁の巡視船は振り切られてしまう。最終的に追尾できたのは海上自衛隊の護衛艦「はるな」「みょうこう」だけで、政府はついに史上初めての「海上警備行動(海警)」を発令。領海内で沈黙のまま停止している不審船に対して、「みょうこう」の乗組員が立ち入り検査を行うことになった。
ところが護衛艦の乗組員は近接戦闘の訓練など受けておらず、そもそも防弾チョッキさえなかった。この状態で突入するのか? 本書は緊迫のその艦内を克明に描写する。
約200人の乗員のうち、決死隊は約20人。10分の1で当たる「貧乏くじ」といいっていい。 「オレかよー」「マジ?本当にやんの」「やんないはずじゃないのか」。決して大声にはならない、しかし、不安の湿り気を含んだ声で食堂はざわついた。
集まってきた隊員を見て、伊藤(「みょうこう」航海長)は息を飲んだ。カポックと呼ばれる救命胴衣の下の腹に、『少年マガジン』などの漫画雑誌をガムテープでぐるぐる巻きにしていた。防弾効果はさほど期待できない。気休めでしかない。だが、防護衣はないのだ。陸自が部隊からかき集めて持っていく用意はしていても、実際には届いていない。だから、彼らは漫画雑誌を巻くことで覚悟を決めたのだ。
由岐中「みょうこう」船務長は、志願して決死隊の指揮をとった。当時39歳。著者のインタビューで「そうか、やはりあの時は死ぬことを意識したんだな」と聞かれ、こう答えている。
「うん。もうひとつ思ったのは、『しょーがねーな』っていうこと。防大入った18のときから、育ててもらったとオレは思っている。でも、こうなるのも国の意思だ。いま立ち入り検査とかやってもたいした成果は得られないかもしれないけど、でも、それはそのときの国家意思なんだから、しょーがねーか、と。しょーがねーというのかなぁ……いや、あとで少しばかりカッコいい言葉に言い換えれば『百年兵を養うは……』っていう言葉になるんだろうけど、実際、その時思ったのは、しょーがねーよな、って。そういうものなんだよな、逃げも隠れもできないよな、って」
『百年兵を養うは』というのは、山本五十六連合艦隊司令長官の名言だという。「百年兵を養うは、ただ平和を護らんがためである」。そして自衛隊員たちがまさに突入しようとした時、突如として不審船は動きだし、領海の外へと去った。決死隊は死なずにすんだのだった。
著者は、自衛隊は変わってきたという。戦闘ということが現実的な可能性ではなかった1980年代。90年代にはいってPKOがスタートし、戦地イラクに派遣され、「殺す/殺される」「撃つ/撃たれる」ということがリアルになっていく。そのリアルを自衛隊は受け入れ、制度的にも精神的にも準備と覚悟を進めていったのだという。
「戦闘」と「死」というものをリアルに考えるようになっていったのだ。それがこの20年の自衛隊の道のりだったのだという。著者は書く。
陸自は組織として、隊員の「死」に対する準備を進めていった。私はそれを「死の内在化」、あるいは「制度化」と呼ぶことにしている。
そうやって覚悟を決めてきた自衛隊のリアルについて、私たちはほとんど目を向けてこなかった。国会やマスコミやネットでは「自衛隊員のリスクは高まらない」「自衛隊員を死に追いやるのか」と議論がおこなわれ、しかしそれらは政権批判の材料だったり、自分の主張を押し通すためのものであったりするばかりで、みな「自分の空想の中の自衛隊員」に憑依しているだけだ。議論はつねに空中戦になってしまう。
自衛隊という軍隊を私たち日本社会が引き受け、どう関係し、どうやってともに歩んでいくのか。その議論をするためのまず最初の土台として、私たちは自衛隊のリアルにもっともっと目を向け、真摯に向き合うべきだと心から思う。
「自衛隊は、本当に撃てるのか」。著者は、自衛隊をすでに退官した同級生に聞く。短い答が返ってくる。「やるさ。おれたちはこれまでずっとキツいことをやってきた」
